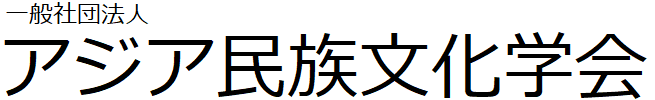化け猫キャラクターにおける身体イメージの解体と再構築
―説話文芸から二次元表現への変遷―
李 瑀琪
化け猫は、東アジアの中でも日本以外ではまれな、日本的な妖怪である。中世にはまだ「化け猫」という言葉は存在しなかったものの、猫をめぐる奇妙な説話が数多く語られていた。『本朝世紀』や『今昔物語集』には、村を襲い人を食い殺す巨大で凶暴な猫が登場する。これらの猫は、人間の倫理規範を逸脱した暴力的存在として表現され、猫の「動物的身体」が不気味さの源泉として強調されていた。また、毛色や目、鋭い爪など、動物的な身体特徴が執拗に描かれ、人々の恐怖を喚起していた。
注目すべきは、藤原定家の『明月記』で初登場する猫又である。猫又は尻尾が二股に分かれるという身体的変異を持ち、人間の身体から逸脱する異形の象徴となった。この身体的異常性は、猫が単なる動物から妖怪へと変容する契機となり、猫の身体そのものが境界的な存在として機能することを示している。
江戸期に入ると、化け猫の最大の特徴は「人に化ける」という身体変容となる。鍋島藩の化け猫退治伝説では、猫が女性に変身する「女体化」が中心的な要素である。この変身は、猫の身体が女性性を帯びることで、同時代の女性嫌悪や性的恐怖を象徴するものとなった。特に老女が化け猫に変化する描写では、女性性の喪失と異形化が描かれ、身体的な境界が曖昧になることで恐怖を増幅させている。また、江戸期では妖怪が視覚的な娯楽の対象となり、化け猫もキャラクター化が進んだ。歌川国芳をはじめとする浮世絵師たちは、化け猫に視覚的な身体イメージを与え、その女性的な身体性が強調された。
昭和期には怪猫映画が登場し、猫の身体と人間の身体が交錯する描写が強調された。入江たか子が出演した映画では、女優(人間)が猫(動物)を演じることで、身体の境界が曖昧になり、自由に身体転換する化け猫の主体性が描かれた。この時期の怪猫映画は、女性の復讐を描くことで、男性が女性に対する恐怖を投影する作品が多い。
戦後、水木しげるらの視覚作品により妖怪キャラクターは親しみやすさを持つようになった。90年代以降は萌文化の影響で「萌え擬人化」が進んだ。例えば「東方プロジェクト」の橙のような猫娘は、猫耳や尻尾を持ちながらも少女的な身体を持つ。これにより、伝統的な人間像から切り離された新しい身体イメージが構築され、妖怪と人間の身体は互いに溶け合う形で再構築された。
否否可の様式に表れるシャーマンの視線
生駒 桃子
中国少数民族の喪葬歌に確認できる「Aは(○○だから)だめ、Bは(××だから)だめ、Cは(△△だから)よい」という形式を、遠藤耕太郎(『古代の歌』瑞木書房、2009)は「否否可の様式」と名付けた。
この否否可の様式は『古事記』においても四例(①イザナキによる禊ぎ場面、②記4番歌(八千矛神による須勢理毘売を讃める歌)、③記42番歌(応神天皇による矢河枝比売を讃める歌)、④記43番歌(応神天皇による髪長比売を讃める歌))確認できる。
古橋信孝(『万葉集を読みなおす』NHKブックス、1985)が指摘したように、これらの様式の基層に、南島歌謡「祓い声」等にみられる巡行叙事の様式があることは確かだろう。ただし、「祓い声」における否否可の様式は、神に見出されてなされた村の始原(村立て)を語るために用いられるものであり、①や中国少数民族の喪葬歌にみられる否否可の様式を説明しつくすことはできない。
本発表では、否否可の様式の論理を「祓い声」にとどまらず、東アジアに広がる様式と捉え、そこには、あの世とこの世を媒介するシャーマンの視線があることを考えてみたい。
「マイナスを語る神話」の再検討
―『ゾミア』を読む―
岡部 隆志
筆者は1998年怒江流域に住む少数民族の神話に、漢族に対して自らが劣っているとする内容の神話があることに興味を抱き「中国雲南省怒江流域の創世神話―自らのマイナスを語る怒族・独龍族の神話」(『共立女子短大文科紀要』45号・2002年、『神話と自然宗教』2013年)という論を書いた。中国の周辺地域の少数民族に自らのマイナスを語る神話があることは工藤隆や他の研究者も報告している。筆者は少数民族が何故このような語り方をするのかいろいろ考えたがうまく説明できなかった。だがジェームス・C・スコット『ゾミア』(2013年)が出版され、スコットは、自らのマイナスを語るこの型の神話は、国家の支配から山岳地帯へと逃れた少数民族が、国家というシステムを作らないための語り型であると意味づけた。この本はそれまでの東南アジアや中国西南地域に住む少数民族研究に衝撃を与えたが、私もその衝撃を受けた一人である。特に私の「自らのマイナスを語る神話」解釈は再検討を迫られている。本発表では、その再検討と共に『ゾミア』をどう読んだらいいのか、私なりの見解を述べて見たい。