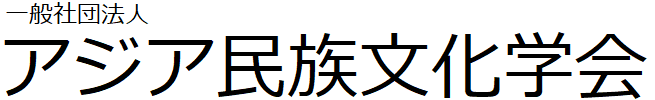【シンポジウムの趣旨】
日本人は風土記の昔から歌を掛け合ってきた。風土記には歌垣の習俗が記録されているし、万葉集にも掛け合い的な歌が収められている。連歌や連句などもその場で歌をつないでいくという点で掛け合い的な要素がある。このように、日本人の「うた」には近代にいたるまで長きにわたって言葉を即興で編んで歌を掛け合う風習があった。だが近代に入って西欧を模範とし、徳性の涵養、国民教化を目指した学校教育のなかではこの歌による言葉のコミュニケーションという考え方が失われ、クラシック音楽にみられるような決まった歌詞と音楽による独唱と合唱が歌のイメージを支配することになった。連歌や連句はほそぼそと行われてはいるが、日本人の視野からはうたによる掛け合いがほとんど消えてしまったかのようにも思える。
今回のシンポジウムではこのような現状を改めて考えるため、音楽教育学者として掛け合い歌を日本の音楽教育に取り込む試みを行ってきた伊野義博氏と、伊野氏らとともにブータンの学校における掛け合い歌の実践を見てきた権藤敦子氏を迎え、掛け合い歌の実践と伝承について考える。そこでまず秋田県の掛唄と民謡の変遷と伝承の現状を事例に、民俗的世界における「うた」の変化について見ていく。次に今の日本の学校における音楽教育に歌の掛け合いを導入する試みから見えてくるそのむずかしさを明らかにする。続いて照葉樹林文化論で提唱された「歌掛け文化圏」の西端に位置するブータンで学校教育に歌の掛け合いが導入されている事例を検討し、なぜブータンでは掛け合い歌が自然と学校の中で実践できているのかを見たうえで、日本の大学でバーチャル空間に掛け合いの場を作る実践から見えてきたことについて考察する。
本シンポジウムを通じて、日本の伝統的な歌文化に通底する言葉の掛け合いがどのように継承されているのか、実践を通じてなにがどのように継承され、なにが消えていくのかを考えていきたい。 (梶丸岳)
【シンポジウム発表要旨】
「うた」から「民謡」へ
~掛唄と秋田民謡はどこで道が分かれたのか
梶丸岳(京都大学)
日本の民謡はかつて「うた」だった。それはまさに民謡の定義として言われるように、生活の中で唄われ、旋律は素朴でさまざまな個人的な違いを大きく許容し、むしろ歌詞において表現が評価され時に競われるものだった(Hughes 2008)。奄美の歌遊びや八月踊りで唄われる掛け合いの歌や、秋田県に残る即興の掛け合い歌「掛唄」はそうした「うた」の生き残りであると考えられる。
だが二十世紀を通して社会や生業は大きく変貌し、「うた」の息づく生活自体が失われていった。それと並行して「うた」がラジオやテレビで流れるようになり、数度の民謡ブームを経て「うた」がステージに上がって「民謡」と呼ばれるようになると、それは決まった歌詞に決まった旋律で唄うべきものとなり、音楽上の技巧を凝らし、教室で師匠について習うようなものに変容していった。
本発表はこうした歴史を跡付けるとともに、民謡からいかに掛け合いが失われていったのかを明らかにしていく。そして、民謡の現在地について改めて問うていきたい。
学校教育における掛け合い歌
~実践の難しさとわずかな展望~
伊野義博(新潟大学)
日本の学校教育において、掛け合い歌を実践することは容易ではない。音楽授業における歌唱教材は、主として完成作品であり、作詞・作曲された曲をいかに表現し相手に伝えるかが重要なねらいとなっている。その結果、旋律や歌詞の固定化、表現者から聴き手という一方向の関係性が生まれやすい。発声や発音、強弱等の技能が重視される。これらは、即興性、旋律や歌詞の流動性、双方向性、当意即妙な受け渡しや修辞法の活用といった掛け合い歌の世界とつながりにくい。
歌の交換(交感)によるコミュニケーション、仲間との関係性の中で新しいものを創り出す、など、教室で双方向的な歌の有り様を創り出すことは重要である。日本の音楽教育は大きな忘れ物をしてきた。しかしながら、現行教科書教材においても、わらべうたや民謡、あるいは、西洋的語法による曲でさえ、「掛け合い」の視点から教材化することは可能である。現場教師とともに実践した掛け合い歌の事例を紹介しつつ、その可能性を探る。
ブータンにおける掛け合い歌の現在
権藤敦子(広島大学)
ブータンは中国とインドの間にあるヒマラヤ南麓の王国で、チベット仏教の影響を強く受けてきた。チベット系住民、ネパール系住民、ブータンの先住民など、多民族・多文化で構成されるとともに、高い山と深い谷に阻まれ、九州と同じくらいの広さの国内には約20の言語が存在すると言われる。しかし、掛け合い歌の存在はブータン全域で確認されており、古くは中尾佐助(1959)によって「即興の歌詞に節をつけて、恋の歌のかけ合わせの歌合戦をやる。日本でも王朝時代に歌垣と呼ばれた風習である」と紹介された。歌垣に加え、占い遊びや子どもの成長を祈る行為、双方向的に展開される対面伝達行動として、掛け合い歌は各地で行われてきた。
ここでは、約15年になるブータンでの共同研究(代表:伊野義博)の成果を踏まえ、ブータンで伝承されてきた掛け合い歌の現在について取り上げるとともに、日常の文脈から離れ,かたちをかえて実践されている近年の事例(学校行事等)を紹介する。
VR歌垣ゲームの実践を通して
遠藤耕太郎(共立女子大学)
東京にある勤務先の女子大学で、2023年度から文学系と教育工学系の複数の教員と学生を交えて、VR(バーチャル)歌垣ゲームなるものを制作している。本発表ではこの実践を通して見えてきた歌を掛け合う文化の継承のあり方について報告する。
日本列島には、古代には歌垣という恋歌を掛け合う行事があり、その歌を掛け合う技術や楽しさはその後の『万葉集』以降の問答歌や贈答歌、さらに連歌、俳諧、連句などへと継承されてきた。私はその継承の核には、虚構性、ストーリー、歌を連結する技、ゲーム性という4つの要素があると考えている。これらの要素は日本列島の歌垣と地続き(海続き)の長江流域の恋歌を掛け合う行事にも確認することができる。その4要素をVR空間でアバターが18首(つまり半歌仙)の恋歌を掛け合うゲームとして制作したのがVR歌垣ゲームである。それを現在の女子大生がどのように実践し、楽しめるのかを報告したい。