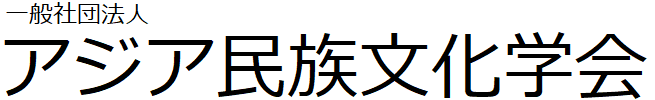遠藤耕太郎氏の『万葉集の起源』が志田延義賞を受賞しました
本学会の代表理事、遠藤耕太郎氏の著書「万葉集の起源 東アジアに息づく抒情の系譜」(中央公論新社、2020)が、第38回志田延義賞を受賞しました。
日本歌謡学会 令和3年度春季大会(2021年5月23日)にて授賞式が行われました。

遠藤氏「受賞の言葉」(2021.5.23授賞式)より
私の著書『万葉集の起源』が、伝統ある志田延義賞をいただきました。
一言、ご挨拶申し上げます。
『万葉集の起源』は副題を「東アジアに息づく抒情の系譜」と申します。万葉集から1300年を経て現代にまで続く日本人の抒情、感性が、どのように育まれてきたのかといった意味で「抒情の系譜」と名付けました。「抒情」というと近代の文学概念のようなニュアンスもありますが、何かに心動かされる、心の揺れのようなもの。今風に言えば「心が震える」(逢いたくて逢いたくて震える)といった感じです。そういうものを、言葉にして伝える技術といった意味で用いています。
そういう抒情の仕方は、日本独自のものではありません。おととし、元号が「令和」に決まった際、当時の総理大臣は典拠とされた『万葉集』が「国書」であることを強調していましたが、その『万葉集』の歌の抒情の仕方は、広く中原の辺境地域に生きる人々の抒情の仕方とつながっています。
かつて冊封体制の中で、日本は「倭」という蛮夷だったわけですが、中原の西南にもさまざまな蕃夷が暮らしていました。その人々の末裔が、今は中国の少数民族とされて暮らしています。
私は97年から彼らの村に入って、彼らの歌や神話を調査してきました。当時、文字はごく限られた人しか使いませんでした。電気もありませんでしたから、テレビなんかもありません。口頭の歌が、歌垣とかお葬式でたくさん歌われていました。
そういう歌をビデオに撮って、一句一句翻訳していくという作業を続けてきたわけですが、だんだんとわかってきたことは、彼らの抒情の仕方は『万葉集』の歌のそれとあまり変わらないということです。それは一言で言えば、ストーリーとそれに抗する歌を組み合わせるということです。共同体的なストーリーを歌の中に作り上げたうえで、そのストーリーに逆行する思いを挿しはさんでいくという方法です。歌垣歌にもお葬式の歌にもそれが見られ、それは『万葉集』の歌、雑歌にも相聞にも挽歌にも見られるのです。私はそういう抒情は、心のバランスをとる技術なのだろうと思っています。
さて、日本歌謡学会のなかにも、牛さんのように中国少数民族の歌を研究なさったり、また台湾の歌にまで大系的に研究の幅を広げるといった動きが見えています。数年前の志田延義賞が工藤隆先生の『歌垣の世界』に送られたのもそういう流れの中にあるのだろうと推察いたします。工藤さんのご本の副題は「歌垣文化圏の中の日本」というのでしたが、東アジアの辺境民族の歌文化のなかに、日本の歌文化を位置づけるということです。
すでにそういう研究が日本歌謡学会でも、それからアジア民族文化学会でも、たくさんの成果を収めてきています。今後、歌謡を一国の文学史に押し込めるのではなく、「東アジアの歌謡学」のような、新たなステージで捉えていく必要があるのではないかと思っています。
私のこのたびの本が志田延義賞を受賞したことの意義も、おそらくここにあるだろうと思います。そういう意義をお考えになってくださった審査員のみなさま、また会員のみなさまに御礼申し上げます。
このたびは、どうもありがとうございました。