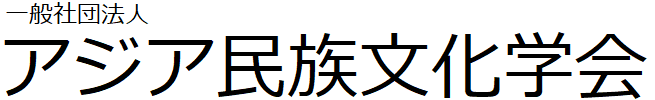1
アジア民族文化学会は、日本古代文学・日本古代史・民俗学・芸能史・宗教学・文化人類学・中国学・東洋史・言語学・映像人類学ほか、さまざまな専門領域の人々から成る約220名の会員で、2001年5月12日に設立大会を開いて発足した。この学会の前身の「少数民族文化研究会」(1997.2~2001.5)の運営を担う中心的な一人が私だった関係で、総会の席で私が初代「代表」に選任される運びとなった。代表の仕事の一つは「挨拶」をすることでもあるので、以下、この学会の設立趣旨の再確認という意味も込めて、少々長めの挨拶文を書いてみることにした。この学会は設立直後なので、規約や運営組織などに未確定の部分がいくつかある。たとえば、代表や運営委員の選出方法や任期についての規定ができていない。選挙制度の導入という点では、特に運営委員の場合は会員がかなりの数にならないと委員の確保自体が難しくなるので、今後の会員数の伸び次第で導入ができるかどうかが決まるであろう。任期については、少なくとも代表については3年くらいがいいのではないかと、総会で発言しておいた。こういったことも含めて、これからの3年間くらいを目処に、会員諸氏からの意見・アイディアなども参考にしながら、少しずつくふうして学会としての形を整えていきたいと思う。これら以外にも、当学会は今まさに草創期にあるので、会員諸氏からのさまざまな支援が必要である。この学会の成長には、ボランティア精神と行動力を持った会員の協力が不可欠である。もちろん最も重要なのは、大会発表そのものの充実と、機関誌(『アジア民族文化研究』という誌名になる予定)の充実とである。そのうえでの話だが、大会運営と機関誌発行の裏側には、大会当日の運営や機関誌の編集雑務はもちろんのこととして、それらについてのさまざまな雑務が年間を通して行われている。これらの雑務の一部を引き受けようとする会員が、少しでも多く名乗り出てくれることを期待している。
なお、「学会通信」のようなものの体裁が決まっていればこの挨拶文はそれに掲載されるべきだろうが、今回は間に合わなかった。いずれその「学会通信」が会員の自由な意見発表の場になればと思っている。
2
さて、この学会はさまざまな分野の人々から成っているが、会員のこの”幅の広さ”をプラスの方向で活かせるかどうかが、これからの鍵であろう。 幅の広さということとの関連でいえば、近年”学際的”という言葉がよく用いられている。しかし、複数の既成の学問が集合してそれぞれの独立は維持したままで”混合物”を作る研究形態を脱し、それぞれの独立性に変質を生じさせて今までにはなかった新しい”化合物”を作る研究段階へと進むには、それにふさわしい新形態の学会が必要なのではないか。アジア民族文化学会は、すでに各分野に専門領域の学会があるのだから、そういった種類の学会をもう一つ増やそうとして発足したのではない。そうではなくて、細かい専門領域は既成の学会に任せ、この学会では、それぞれの専門領域を背景に持ったうえで、さらにその領域を超えて別の専門領域とも交流できる場を作ろうと意図しているのである。すなわち、最初から”領域を超えて交流する”ことを目的にしている学会なのだ。その際に、最終的に外さない一つの条件を付けた。それは、低生産力社会の民俗文化の、現場の”第一次資料”にこだわることである。このような意味でいえば、アジア民族文化学会は、第一次資料の現場性の深さを武器にして領域を超えて交流する、そのことを”専門”とする学会だとしていいだろう。
3
以下、話を具体的にするために、日本古代文学を専門とする私の事例で述べさせていただく。
私は長いあいだ古代文学会ほかいくつかの古代文学の学会に所属すると同時に、民族学会(文化人類学)や民俗芸能学会などにも所属してきた。日本最古の書物『古事記』を読み解くにあたって、どうしても無文字の時代の日本列島民族の言語表現についてのモデル作りが必要で、そのためには未開社会などの無文字の神話や歌垣などの実態について知らねばならなかったからだ。したがって、1973年以来所属してきた民族学会には特に期待するところが大きく、いつの日か、低生産力社会の村落で実際に生きている神話や、歌垣など歌掛けの実際が、歌詞の全体と現場状況を丸ごと紹介する形で発表されるのを待っていたが、なかなかそういうものに出会えない。文化人類学の論文として発表されるもののほとんどは、それらの歌詞のダイジェストや、それらが歌われる状況の概略についての言及だけだった。にもかかわらず私は、自分から現実の未開の村落にまで足をのばそうとはしなかった。そういう資料は、いつかきっと文化人類学者が豊富に提供してくれるだろうと期待したまま、私は現在の日本国の国境の、せいぜい沖縄県までに限って祭式の現場を追って動いていただけだった。厳しく言えば、他力本願だったのである。そうこうしているうちに、私の英語やフランス語・ドイツ語の能力は衰え、ましてや新たに中国語や各地の少数民族語に習熟しようなどという情熱もなくなっていった。古代ヤマト語と少数民族語の比較には言語学が必要なことも徐々にわかってきたが、それは、専門の言語学者に手伝ってもらえばいいと考えていた。ここでも厳しい言い方をすれば、要するに怠惰だったのである。仮に、このように他力本願と怠惰に安住していたその時期の私が、文化人類学の研究者と共同研究に入ったとして、その学際的研究がどれほどの成果を上げたかといえば、今ならかなり否定的にならざるをえない。そういう共同研究は、自分の専門領域を頑なに守ったうえで、別の領域の学問成果を都合のいいところだけ切り取って持ってくる、つまりは単なる”混合物”作りということになりがちである。その場合の私は、その”混合物”を得たあとでも、他力本願や怠惰を温存したまま、基本的には国境と日本語と既存の文字資料の内側だけで完結する、研究方法そのものが”国粋主義”的な古代文学研究を続けていたことだろう。
しかし、文化人類学の側からは、ごく例外的な研究を除いて、『古事記』以前の言語表現のモデル作りに必要な”神話や歌垣の丸ごとの現場資料”は、私の目の届く範囲では、ほとんど提供されなかったように思う(実は博物館や誰かの研究室にはあったのに私が知らなかったのだとすれば、それは私の不勉強ゆえであるからお許し願いたい)。その結果、私の内部での焦燥感はほぼ限界に達したようであり、ついに、それなら自分で現場に飛び込んでみようという気持ちになって、1994年9月に中国雲南省を初めて訪問することになったのである。そして帰国後に外国語学校に2か月間通って中国語のにわか特訓を受け、翌95年4月からの雲南省1年間滞在となった。この時期およびそれから以後の現地調査の成果は、単行本『歌垣と神話をさかのぼる-少数民族文化としての日本古代文学』『ヤマト少数民族文化論』『中国少数民族歌垣調査全記録1998』(岡部隆志氏と共著)、現地調査報告記録、論文、新聞原稿、雑誌連載などで随時発表してきた。文化人類学の専門家からみれば、それまでこの分野でほとんど実績のなかった”素人”の仕事がなぜこれほどに次々に公刊され、発表されるのか、不思議に感じられたことだろう。しかし、むしろこれは、私が”素人”だったことがプラスに働いて、新しいものが見えたからだと考えてもいいのではないか。
専門領域の学会・学問界というものは、それぞれが歴史と伝統を背負い、その分野の研究の蓄積の上にさらに精密さを加えていくのが普通だ。それはもちろんその学会・学問界の成長・発展でもあるのだが、一方で常にタコツボ【注:丸山真男「タコツボっていうのは文字通りそれぞれ孤立したタコツボが並立している型であります。近代日本の学問とか文化とか、あるいはいろいろな社会の組織形態というものがササラ型でなくてタコツボ型であるということが(略)」『日本の思想』岩波新書、1961】の中での自閉と停滞の危険を背負っている。学問としてはどんどん精密になっていたはずなのに、ある時気づいたらその学問の全体が無用な存在に変わっていたということもありうるのである。また、古典文学研究の場合によく生じることだが、その作品の本質を把握するためには、まずその土台を固めなければならないということがあるのだが、しかしいつのまにかその土台作りが自己目的化されて、いつのまにか作品の本質分析のほうは忘れられてしまうことがある。『古事記』など日本古代文学の作品でいえば、これらはすべて漢字だけで書かれているので、その漢字の数、種類分け、日本発音と中国発音の比較そのほかの基礎作業的研究がある程度深まっていなければ、本質分析も空疎なものとなる。しかし、その程度が「ある程度」を超えてそれ自体が最終目的であるかのように錯覚されてくる傾向がある。こうなると、本来は家を建てるためにその土台(基礎)を作っていたはずなのに、いつのまにか、土台しか作らない建築家が大多数になるということになる。土台は徹底的に精密かつ堅固に作るが、その上に建つはずの家屋本体については無関心、あるいは嫌悪するといった現象さえ見えてくる。これは、日本古代文学研究というタコツボの中で、そのタコツボのさらに一部分の作業部門がタコツボになるということであろう。タコツボ状態があまりに長く続くと、学問は土台(基礎)と本質分析の両方がそろって初めて学問になるという当たり前のことが見えなくなり、結果としてその学問の全体が腐る。 学会に限らず「タコツボ型」社会というものは内向きの目しか持たないため、仮にその学会が”緩慢な死”に向かっていたとしても、自覚することさえできない。しかしそういうときにしばしば、”素人の目”とか”初心者の目”といったものが思いがけない突破口を開くことがある。
もちろん私は、日本古代文学の領域ではそれなりの専門家である(伝統的な文献至上主義研究の立場からみれば、私を専門家として認めないという人もいるだろうが)。その日本古代文学という専門領域の内側ではどうしても解決できない壁にぶつかり、それを突破する方法を渇望し続けてきたという歴史が私にはあった。その渇望が、同じ少数民族文化に接しても、私に文化人類学者とは別なものを見させてくれたのかもしれない。要するに、専門領域を持ちつつ、一方でその専門領域に欠如感も抱く感性が、異分野に接したときに”素人の目”として新たな視点を切り開くことになるのであろう。
4
ところで、日本古代文学の学会・学問界のなかで私がなぜ欠如感を抱くようになったかだが、その理由の一つには私の人生経歴からくるものがあったかもしれない。学部は経済で、主にマルクス経済学を学んだが、それにのめり込むことにためらいも感じてむしろ文学・演劇に傾斜した。大学院では演劇学を専攻して主に歌舞伎研究に没頭し、同時に劇団を結成して現代演劇の演出・劇作・評論に従事していた。そのうちに研究対象が、歌舞伎・浄瑠璃から中世能楽へ、さらに平安期を経て奈良期へと移って日本古代文学に落ち着き、主に『古事記』の研究をするようになった。このような経歴を伝統的な”国文学者”の目で見れば、私はやはり”素人”に見えることだろう。しかしおそらくその”素人の目”が、私に、国文学者一般には生じることの少ない渇望感を与え、中国辺境へと日本の国境を越えさせたのだと思う。
というわけで、学際的研究とは、それぞれの専門領域でそれなりの仕事ができるようになっているのに、しかしそのタコツボのなかで生きていることに息苦しさも感じる感性を持ち、さらにそれが何ものかへの渇望となってついにそのタコツボの外の世界も見てみようと実際に行動してしまうところに生じる現象である。ただし、よく聞く言葉に、あまり早くから領域を超えようとすると”根無し草”になってしまうので、まず自分の専門領域でしっかりと足元を固め、そのうえで異分野へと足を踏み出すのがよい、という言い方がある。しかし、タコツボの中でそれなりの権威者になってしまったあとでは、それまでに築いた堅固なタコツボの殻を壊すことができなくなるのが普通だ。あるいは、土台作りの技術の習得に努力しているうちに、いつのまにか土台以外のものは作れなくなり、家屋本体を建てようという気持ちは残っていても、肝心の家屋は建てられなくなるということもあるようだ。土台(基礎)作りに必要な技術とは別の技術が家屋本体作りにも求められ、しかもその技術の習得には土台作りの場合とかなり異質な訓練が長期にわたって求められるのである。 実は、異分野と交流するにもそれなりの”年季”が要るのである。若いうちから、異分野を視界に入れつつ自分の専門領域を深めていくという研究態度の積み重ねがあって初めて、学際的研究が新たな”化合物”の創造へと向かう。タコツボの中で専門技術の作業的学問だけを鍛え込んで長い年月を過ごすと、それが習い性、型となってしまい、その型は、中高年になって、まして大学教授などという肩書きも持ってしまったりするころには、とても変更不可能なものに見えてくるものだ。そして老年になると”円熟”を求めたりして守りに入ることが多いので、その人の学問の進化はその段階で終わることになる。領域を超えるためには、それぞれの専門領域でそれなりに自立する能力を持ち、同時にその専門領域の内側だけの世界に欠如感を抱く感性を持ち、その欠如感をバネに領域を超えてさらに大きな世界へ踏み出そうとする志の高さを持ち、そしてそれを実際に行動に移す勇気を持つことが必要である。「志の高さ」とまで言うと褒めすぎだと言われるかもしれないが、しかし一般には、たとえば就職のことを考えると、タコツボの中の掟を破って他郷に足を踏み入れただけで指導教授の不興を買う危険もあるのだから、やや大げさに言えば”学問に殉ずる”といった側面のあるその姿勢は、少しばかり高く評価してもいいのではないか。 ところで、現地の第一次資料にこだわるという点についてだが、もちろん、実際に辺境の集落に足を運ぶことには、さまざまな障害と困難があり、誰でもが入れるものではない。しかし、自己の内部に欠如感を持ち、自己の殻を破ろうとする意志さえあれば、実際に現地に入っているかどうかは副次的な問題になるだろう。むしろ、現地に入っていないがゆえに、他の研究者によって報告された神話や歌垣の資料に独自のものを発見し、報告者も気づかなかった問題意識を浮かび上がらせることがあるだろうし、また報告者の取材方法への注文や質問なども出てくるであろう。逆にいえば、
現地に入った報告者は、どのようにすれば、現地に入っていない圧倒的多数の人々が利用できる資料を作れるかを真剣に考えなければならないのであって、現地に入っていない人たちからの注文や質問はそのためのヒントを与えてくれるのである。現地に入っていないがゆえに尖鋭化される問題意識というものもあるのであり、これまた”素人の目”の功績であろう。
この学会は、これから20年後、30年後に学問界の先頭に立つであろう意欲的な若い人たちや、中高年だが領域を超えようとする志の高さと勇気を持つ人たちが、知の領域の自在な変容と拡大を暢びやかに楽しめる雰囲気のものにならなければならない。そのためには、タコツボ型社会に特有な階級制と権威主義を極力減らし(人間の組織である以上ゼロにはできないが)、また私の経歴に象徴される”雑多さ”を大事にしたいと思っている。
5
なお最後に、また私の事例を紹介させていただくが、日本古代史の専門家でこの学会の会員にもなった小林敏男氏が前之園亮一氏の「倭の五王の通宋の開始と終焉について──辛酉革命説・戊午革運説から見た場合──」(『古代国家の政治と外交』吉川弘文館、2001)という論文に、以下のように、私の書いたものが引用されていると教えてくれた。
最後に大胆に憶測すれば、倭の五王の王統譜はいわゆる「万世一系」的に創作された 系譜であり、万世一系的な王統思想は四七八年以前に成立していたのではないだろうか。水野祐氏は万世一系的な王統譜は七世紀後半に作られたと説かれているが、最近では工藤隆氏が中国雲南省のハニ族やタイの少数民族の家々に伝わる何十代にもわたる一系的な「父子連名」の口承系譜等の調査・研究にもとづいて、古代の大王家も三世紀以来一系的な「父子連名」の私的な系譜を有していて、それがそのまま国家段階の王の系譜になったという興味深い推論を提示されている。
私の論は、6回連載の「少数民族世界と古代日本」の第1回「神話と系譜」(『アジア遊学』2,勉誠出版、1999)に述べたものである。私が驚いたのは、一般に『古事記』以前の、それも3、4世紀ごろの日本列島の状況を考えるときには、日本古代文学の側が考古学や日本古代史の論文を引用することはあってもその逆はめったにないのに、それが起きたことである。私としてはこれはまったく予想外のことであった。それは、歴史学は、古代の文献資料や考古学の知識以外は信用しないのだと私は思っていたからだ。しかし、よくよく考えてみれば、『魏志』倭人伝の邪馬台国についての記述は240年代で絶え、『日本書紀』「神功皇后摂政紀」六十六年条「晋起居注」が”晋の武帝の泰初二年(266)に倭の女王が朝貢してきた”【注:『晋書』にも266年に「倭人」が朝貢してきたとある】と記した266年から、中国側資料では約150年の資料的空白がある【注:『晋書』には413年に倭国が朝貢して来た、『宋書』倭国伝には421年に倭の五王の「讃」が朝貢して来た、とある】。つまり、この約150年間の日本列島に何が起きていたのかは、考古学資料を除けば、結局のところ構造モデルを作って想像する以外にないのである。
私の「神話と系譜」は、方法としては文化人類学的なフィールド調査による資料を基盤にしている。「父子連名」についての報告は何も私が初めてというわけではない。私の手元にあるものでいえば、たとえば竹村卓二「アカ族の系譜と父子連名」(『東南アジア・インドの社会と文化』山川出版社、下巻、1980)、同「アカ族の父子連名制と族外婚」(『社会人類学年報vol7』1981)は文化人類学的に優れた論文であり、またPaul Lewis”AKHA BALLADS,POEMS,AND SONGS”(DAPA、タイ、1989)も参考になった。しかし「父子連名」を『古事記』の天皇系譜の問題に連動させて論じたのはどうやら私が初めてだったようであり、私が蛮勇を奮って、前之園氏の表現を借りていえば「大胆に憶測」を加えたところが私の独自性になったのだろうか。 つまり私は、いったん日本古代文学研究のタコツボを飛び出して文化人類学に接近したのだが、そのフィールド調査で得た資料を、今度は再び文化人類学のタコツボから抜け出して『古事記』の古層に戻してみたわけである。ところがそれを、前之園氏が、これまた日本古代史研究のタコツボを逸脱して私の論を引用した。これらの一連の流れは、この学会の目指す「専門領域に立脚しつつ領域を超える」例の一つなのではないか。
この学会が、多方面で、領域を超えるさまざまな交流の実現に貢献できることを願っている。
(2001.7.1)