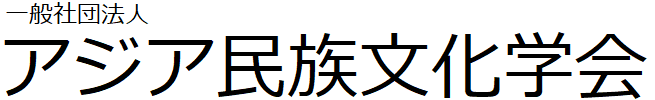私は最近、『日本文学』5月号(日本文学協会発行)に「歌垣における歌とは何か-中国少数民族歌垣文化からのまなざし-」という論を書いた。この論は、「アジアのなかの古代文学」という『日本文学』の特集テーマに応じて書いたものであるが、拙論の一つ前にはやはり同じ当学会の会員でもある西條勉氏の「サンガムと記紀歌謡」という論が載っている。
1997年に工藤隆の案内で初めて中国雲南省の少数民族文化調査に行って以来、私は、特に白族の歌垣文化を中心にほぼ毎年調査に出かけるようになった。それ以来、工藤隆や遠藤耕太郎等とともに、白族の歌の掛け合いを記録し、翻訳し、活字化するという作業を何年もの間続けてきた。そして、掘り起こされた白族の歌垣の実際が、私が専門とするところの日本の古代文学研究にどう活かされうるのか考えてきたが、『日本文学』の論はその報告と言ってよい。とりあえずようやく報告らしい文章が書けるようになった。日本の外に出てフィールドワークするなんて考えもしなかった私にとって、このような文章を書くようになるとは、これは私の人生にとっての思いがけない出来事である。
私は、研究者というよりは評論家と呼ばれることが多いような仕事をしてきたが、花祭や霜月祭、あるいは沖縄の祭に足繁く通い、文学の向こう側にあるような基層文化に関心を抱いてきた。一方で評論家のまねごとのような短歌評論も手がけてきたが、これらに共通するのは、人間や生活の内側に籠もりがちな言葉や心もしくは共同の心性の表現のありようを見つめることである。どちらかと言えば内向きな性格の私に似合ったものであって、だから、日本の外側に出るなんてことは考えなかったし、またそんな機会が来るとも、また自分に出来るとも思っていなかった。それが、工藤氏の導きもあってであるにしろ、雲南省の少数民族文化調査にのめり込み、学会創設にまでかかわってしまうとは、一番驚いているのは私自身である。
実際に少数民族の村に入って、彼等の文化に出会ってみて、私が感じたのは、みな内向きで生きているということであった。伝統的な文化を伝えている少数民族の人たちは、誰も好きこのんで外部と接触したりあるいは市場経済の中で欲望を拡大している、というわけではないということである。一番最初に出会った人々が、中国でも最も貧しく過酷な環境で生きている、リス族・怒族・独龍族であったからかも知れないが、この内向きさの中にある様々な文化を、私は、なんだみんな同じじゃないか、というレベルで受け止めることができた。つまり、日本という世界の生活の営みの中で、さすがに独自だろうと思いこんでいたものを、ほぼ雲南省の生活世界の中で見いだしたのであるが、その同じであることの根拠を、私なりに理解し得たのだ。
それは日本の文化のルーツを雲南に見いだすというものとは全く違う。むしろ、こうやって、地域の中に閉じられながら、それを自分のすべてとして受け入れていく行為と心との結晶によって生み出される文化にそれほどの違いはないという理解である。これは私なりの文化相対主義である。
むろん、調査する側とされる側との格差の上に成り立つ私たちの調査研究が抱える負荷を承知していないわけではない。ポストコロニアルがつきつける最近の文化人類学研究の困難を私もまた共有している。しかし、それが理由で調査研究をやめたという人の話を聞いたことがないのは、誰もがそれぞれの胸の内で調査研究に魅力を感じているからだろうと私などは思う。
文化は多様だけれど、その多様さはレビィ・ストロースが明らかにしたように記号の組み合わせのような差異に過ぎないのならば、あるいは、普遍的なところで違わないのなら、わざわざ外国に行って異文化の人たちと出会わなくてもいいのだし、出会えば、民族とか国家とか歴史とかのやっかいな問題を引き受けて身動きできなくなって暗くなるだけじゃないかと確かに思うこともあった。だが、いったん彼等と出会ってしまうと、簡単にそれをやめてはならないものだと思うようになった。それが何かはよく分からないが、それは他者との出会いの重さ、とでも言うようなものだったと思う。それは私にとって魅力とは言い難いものだけれど、簡単には逃れられないもので私が調査研究をやめない一つの理由ではある。
もうだいぶ前になるが「中日民俗文化学術シンポジウム」の大会の挨拶で雲南大学の学長が、日本の民俗学の創始者柳田国男は民俗学とは貧困を克服する学問であると言っている、とスピーチを始めたのをよく覚えている。地方の調査に行くと共産党の書記長や市長が挨拶で、やはり、自分たちの地域の貧しさの克服を語る。私たちが調査のお世話になった彝族の実力者は、自分たちの彝族の文化について、これが私たちの貧しさの原因だと語った。むろん、彼が彝族の文化を誇りにしていることを私たちはよく知っていた。調査する側とされる側との格差はこんなふうにも現れる。
今年の三月に雲南省弥勒県彝族の火祭りを調査に行った。この火祭りは、奇祭としてかなり有名で、観光バスが村に何台も入り、多くのカメラマンが観光にあるいは取材に来ていた。彼等がいずれも裕福な中国人であることはすぐにわかった。ほとんどが最新式のデジタル一眼レフを持っている。彼等の被写体は祭りだけではなく、農家の庭先で穀物を干したりしている老婆でもある。つまり失われるものを撮ろうとしているのである。九年前に雲南に行ったときには考えられない光景である。格差はすでに中国国内の問題であり、失われていくものへの郷愁や民俗調査がすでに中国社会の課題になっていることを目の当たりにしたのである。
アジアにおける民族文化もしくは民俗研究は、すでにアジア全体の問題になろうとしていることがわかる。良くも悪しくもこれはアジアの市場経済化と近代化がもたらしたものであるが、このような流れの中で私たちのアジア民族(民俗)文化研究は、二つの課題を抱え込むと思われる。一つは、民族や国境を越えたグローバルな社会の中での文化の意味を問い直すことである。もう一つは、閉じられた地域における文化の意味を考えることである。
雲南大学の学長はもう柳田国男の民俗学は貧困の克服を目指すというスピーチはしないだろう。雲南省の民族文化は世界の文化遺産であると誇らしげに語るに違いない。それはそれでいいのだとしても、地域の伝統文化を世界遺産(観光遺産と言った方がいい)として登録する運動が盛んなこの時代の中で、あるいは、外部を貪欲に飲み込み文化の概念を構成する他者性それ自体を消し去りつつある世界資本主義の中でと言ったらいいのか、私たちの文化研究自体がこれまでにない新しい課題に直面していることを知らねばならないと思う。
昨年の夏、大理で山奥に住む白族の村人を招いて西山調と呼ばれる歌謡の取材を行っていたとき、大理に新しく出来た大理学院の白族文化研究所の人たちから来年一緒にシンポジウムをやらないかという申し出を受けた。来年私たちが白族の「石宝山」歌会調査見学旅行をするという計画を聞いてもちかけてきたのだ。大理学院は大理白族自治州の大学であり、白族文化研究に力を入れている。彼等から声を掛けてもらえたのは、私たちも彼等に認めてもらえたという意味でうれしかったが、一方で身の引き締まる思いもした。というのは、私たちの白族文化研究が白族地域にそれなりに受け入れられてしまうということの重さを実感したからである。正直に言えば、私たちの白族文化研究は、日本の古代文学との比較研究が大きなテーマであり、白族の人たちのためだなんて大きなことは考えたこともなかった。だが、テーマがなんであるにしろ、白族の研究は白族の人たちにとって大きな意味を持つには違いなく、白族の人たち自身が、自らの文化の意味を考え始めたときに、外国人である私たちの研究も彼等の社会や生活に何らかの意味を持ってしまうということである。改めてそのことを思い知ったのである。
どんな地域での文化研究も、グローバリズムの中では地域を越えた世界で何らかの意味や形を不可避に与えられてしまうだろうし、また、その地域で生活する人たちの内側に引き入れられ、別の意味や形を与えられるに違いない。
それを前向きにとらえれば、今「アジア民族文化研究」は、激しく変化するアジアの社会に立ち会っているということである。その意味で、私たちに課せられた課題は多い。
私は今回はからずも「アジア民族文化学会」の代表になってしまったが、それは、学会創設にかかわったことや、事務局をやり、東京の中心に勤務しているので会場校の提供が出来るということで選ばれたに過ぎない。任期の3年過ぎたらまた相応しい人に代表になってもらえばいい。ただ、「アジア民族文化学会」に寄せられる期待は大きいと感じている。非力ながらその期待に応えられるよう努力はしていきたい。